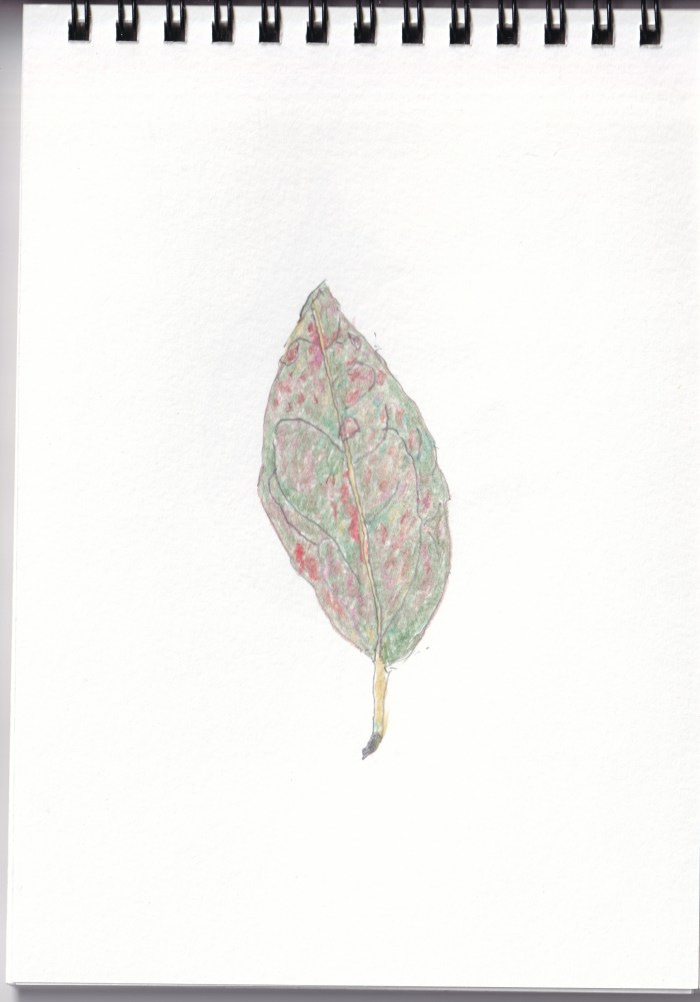今日は暑いらしい。海老名38℃の予定だ。
がの蓋に映りたりああこの時を見張られてゐる
逼塞感ただごとならず隠りゐて便器にしばし便ながしをり
には神様がゐる柱背後に覗く
『孟子』梁恵王章句上6-2 対へて曰く、『天下せざる莫きなり。王夫の苗を知るか。七八月の間、旱すれば則ち苗れん。天油然として雲をし、沛然として雨を下さば、則ち苗浡然として之にきん。其れ是の如くなれば、か能く之をめん。今夫れ天かの人牧、未だ人を殺すことなきをまざる者有らざるなり。如し人を殺すこと嗜まざる者有らば、則ち天下の民、皆領を引いて之を望まん。誠にの如くならば、民の之に帰すること、ほ水のきに就きて沛然たるがごとし。誰か能く之をてめん』と。
王たれば民のことを考えへるべしされば天下与せざるなし
前川佐美雄『秀歌十二月』十月 大伯皇女
二人行けど行き過ぎがたき秋山をいかにか君が独り越ゆらむ (同・一〇六)
二首目の歌である。ふたりともどもに行ってもさびしくてなかなか通り過ぎにくい秋の山を、いまごろ君はどんな思いをしながら一人越えていることであろうか、と大和へ帰る皇子をしのんでいる。秋の山はさびしいものだ。そのさびしさとともに道のけわしさをも「行き過ぎがたき」にそれとなくいいふくめてあるようだ。大事を企てている皇子の心中をおしはかり、心配しているおもむきは前の歌以上に切々として感じられる。これも恋愛情調の強く感じられる歌で、現代式に評するならばあまい歌ということになるのであろうが、さすがは古代である。まっ正直にたがいを信頼しあっている姉弟の心は、そういう語をさしはさむすきをあたえない。単純だけれど心がみちみちている。(略)皇女の挽歌は読むものの涙をしぼらせる。この二つの歌はその」悲劇の序をなすものである。